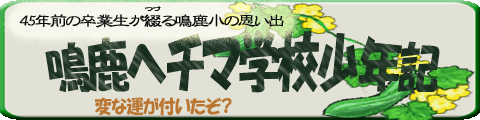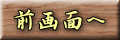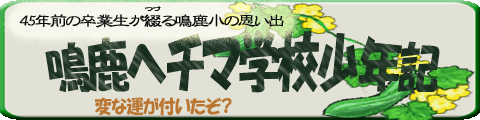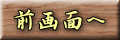【第3章第1話】
下田君と平山君は、背の高さが少し違うために、真ん中にぶら下がっている桶は歩くたびにちょっとずつ後ろ側に移動する。長ぐつをはいて、後ろで棒をかつぐ平山君には分が悪く、次第に肩に重みが増してくる。
避けたはずの(うんこ)のたっぷり入った桶は無情にも平山君に迫ってきた。
「鈴木君、しゃくで桶が動かんように横から引っ張ってくれんけ!」
おぼつかない足取りの平山君が、苦しそうに泥亀みたいに首だけをこちらに向けてすがるような目つきで頼む。
もうすでに校舎の半分あたりに差しかかっていた。
「ここでちょっと桶下ろすぞ」
下田君が声をかけて静かに中の物が暴れないように、そっと桶を意識して下に降ろした。担ぎ手の2人の額からは、汗が滝の様に流れ落ちていた。
「鈴木君ずるいな、ぎょうさん入れすぎや、どうも運びにくいわ」
「サービスして入れてやったのに、文句言うなって…ははは」
息を弾ませている、下田君に答えて僕が言った。
|
 |
 |
その時、今まで開いていた教室のガラス窓が、いきなりピシャンとものすごい音とともに閉じられた。位置関係からすると、3年生の教室あたりになるはずだ。
「見てみい、誰も僕らを歓迎せんやろ」
「なあー、中に1人ぐらい”ごくろうさん”と声をかける気のきいた奴はえんのかな、腹が立つ!」
「何やったら、ここに余計めにまいたろか、大サービスで」
三人の腹の虫は、治まりそうにも無い。中でも悪戦苦闘をして、ようやくここまでたどりついた平山君は怒りは頂点に達していた。
「僕らも好き好んでこんな臭い作業やっているわけでねえんやぞ。僕らは、へちまの生育と観察の教材を作るためで、おめらの理科の勉強に協力してやってるんやぞ。誰もせんので仕方なしに犠牲をはろてやってるんやぞ、わかったか!」
窓のガラスが割れんばかりに罵声(ばせい)を浴びせる。彼の顔は鬼瓦になっていた。宿題をなまけてその罰としてのことなどは、もう頭の中にはみじんも残っていない。正義感や奉仕の心などどこにも持ち合わせていない悪ガキ3人だが、体裁の悪さも手伝ってか一気に腹の底から怒りがわき上がってくる。でも本音としては単に理屈を付けてこの時ばかりと問題をすり替えているだけに過ぎなかった。
|
雲が重くたれ込めて今にも一雨きそうな空模様だが、作業を開始したころよりも、更に雲行きはあやしくなってきているみたいだ。風も無く、やや蒸し暑い午後である。
「ほやけど、いやに臭うな」
下田君は汗を拭きながら、鼻をピクピクさせた。
「ほやな、今日はなんでやろ臭いな、もう僕は鼻が曲がりそうや」
後ろになって桶をかついできた、平山君の言葉には実感がこもっていた。
放課後の校内放送が用事の無い生徒は、帰るようにと促している。ここから見える学校の前の道路には、何人かのまとまって下校する生徒の姿が見えた。
「さあ、気を取り直してやるか」
重い腰を上げて、三人は作業を再開した。
【第3章第2話へつづく】
|
 |
|